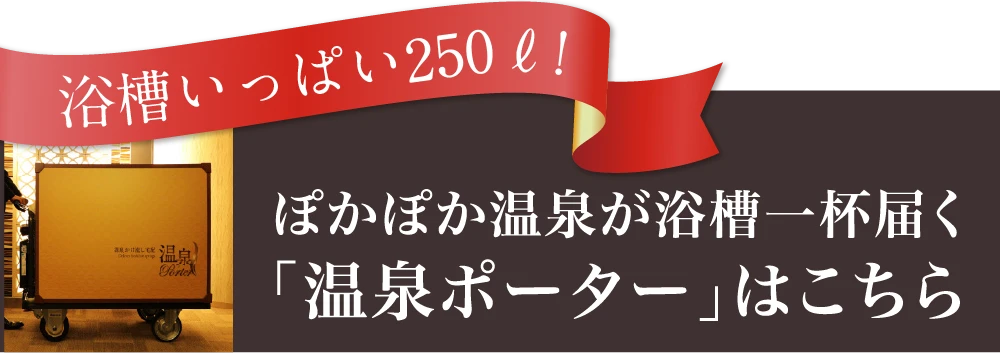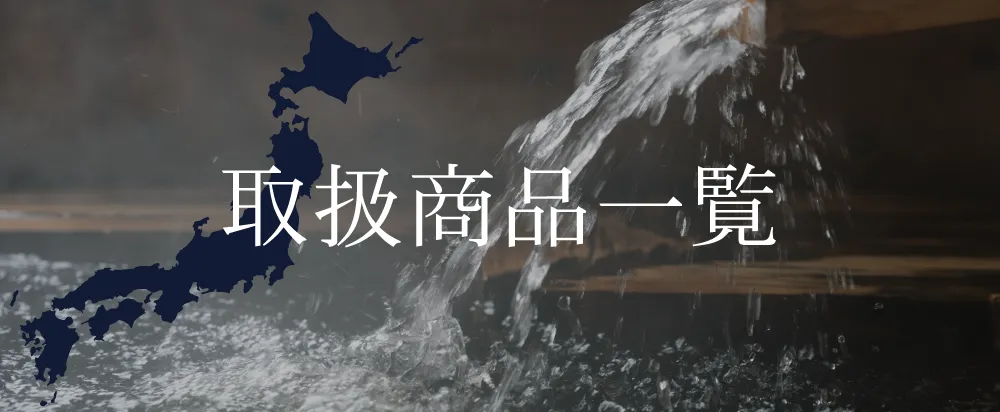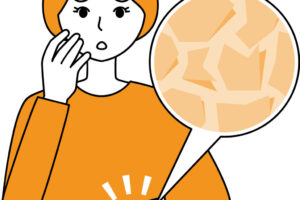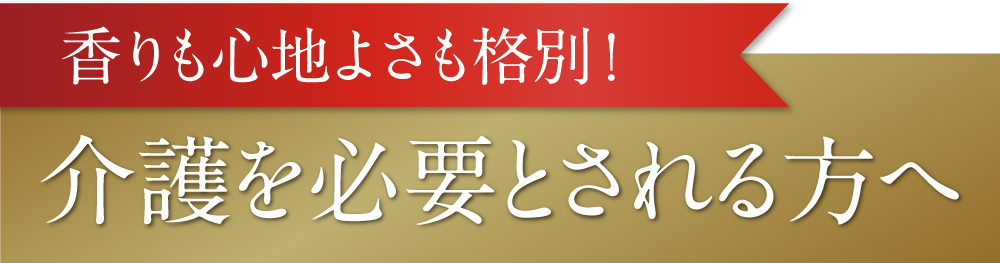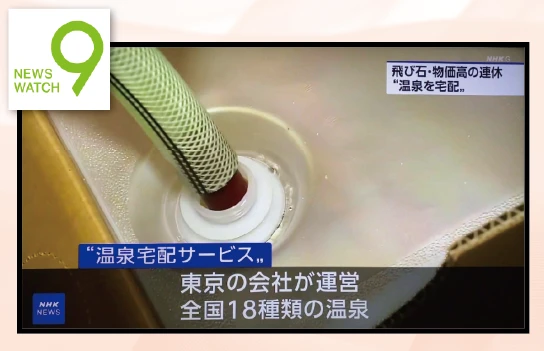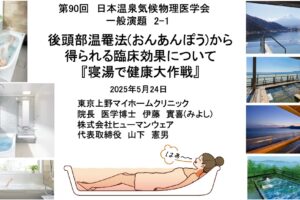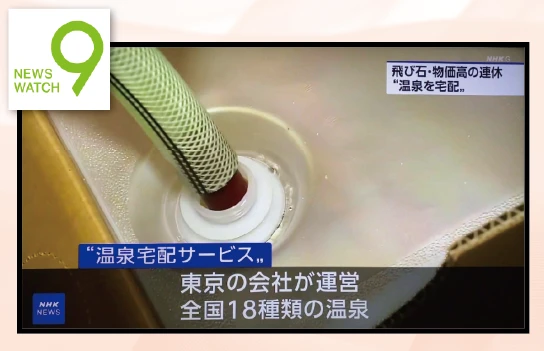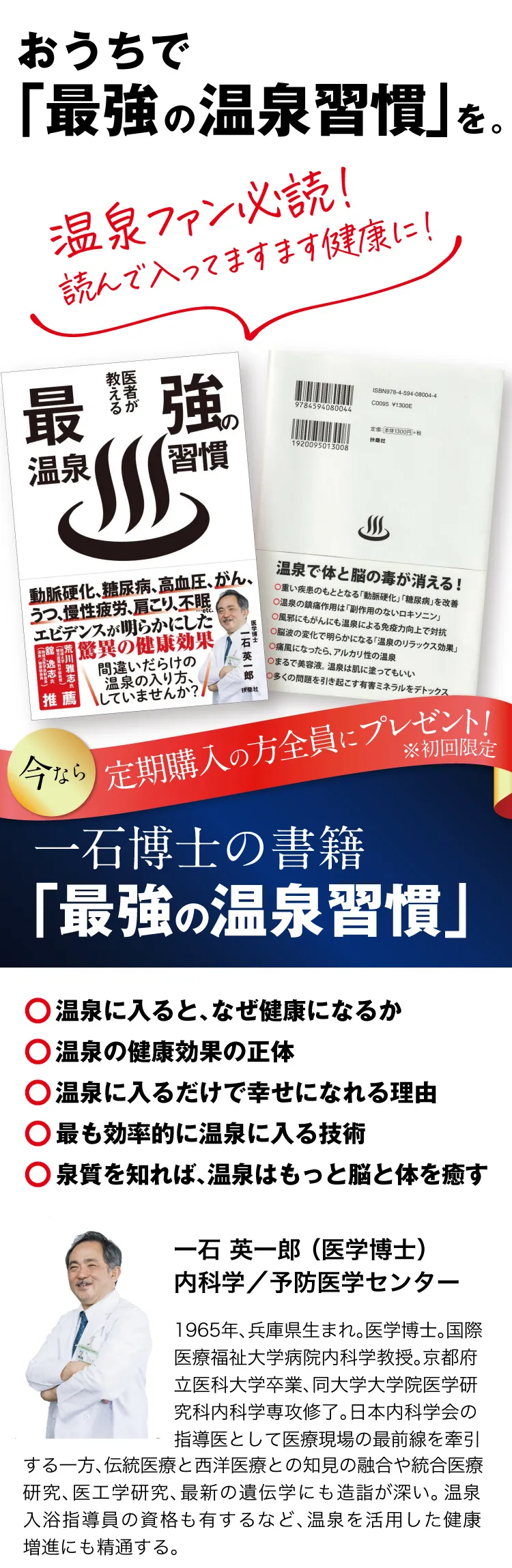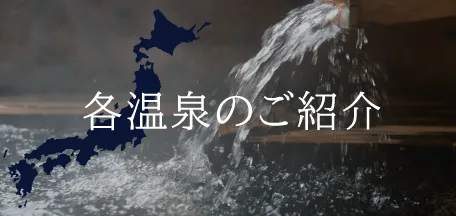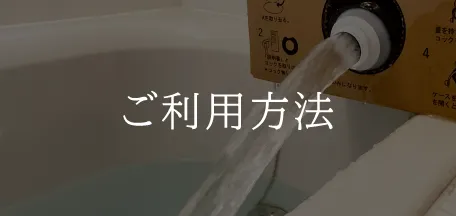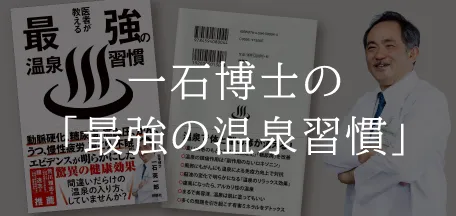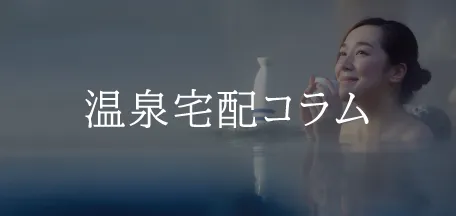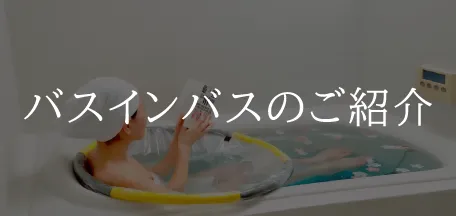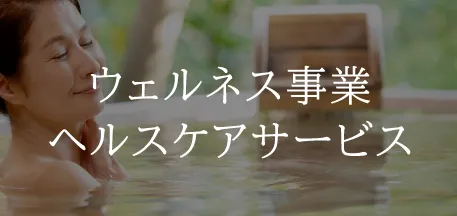徳川家康、御汲湯が起源の「温泉宅配」
―大名気分で満喫する「自宅温泉」の魅力ー
温泉地への旅路は確かに魅力満点ですが、いつも「もっとなんとかならないかなあ」と思うことがあります。
たとえば、
- 家に帰る頃にはすっかり湯冷めしてしまう。
- お湯からあがってゆったりくつろげる場所があるとは限らない。
- 気分よくあがっても、「興味のないテレビを見るだけ」だったりする。
- 帰路は疲れる。
等々、
温泉を出てくつろぐ場所は、自分ごのみにカスタマイズできない、という潜在的なネックがあると言えます。
とくに帰り道は、疲れます。
温泉を出たら、自分に快適な居住空間でゆったりすごしながら、自分の好きな料理と飲み物を片手に、誰にも気兼ねせず、大好きな映画やドラマを観たり、ゲームを楽しんだり、しっかり汗をかいたあとは、そのままぐっすり眠りたい。
そんな願いに応えられるのが「温泉宅配」の魅力だということは
一番 “くつろげる” 空間で愉しむ温泉 -温泉宅配の愉しみ- でお伝えしました。
さて、この「温泉宅配」、いつから始まったか、ご存知でしょうか?
なんと江戸時代、徳川家康の時代にまでさかのぼるのです。

徳川家康は熱海まで温泉に行っていた

関ケ原で勝利した徳川家康が、翌年、西方への旅の途中、熱海温泉に滞在。
同年1604年、病を患っていた岩国の領主、吉川広家に熱海の温泉を五樽、送り届けたことが記録に残っているそうです。
これが、江戸時代、歴史上の記録に残る「温泉宅配」です。
その名も「御汲湯(おくみゆ)」
家康の熱海温泉好きは今も現地に行けばわかります。
熱海駅前にある天然温泉を使用した足湯があります。
この足湯は「家康の湯」と言われ、2004年、家康が熱海に訪れてから400年の記念事業として設置されました。
徳川家康が愛でた熱海温泉を江戸城へ運ぶ「御汲湯」の始まり
家康の熱海温泉好きは三代将軍徳川家光に受け継がれ、1622年、熱海の中心的温泉源である「大湯」の湯を江戸城まで運ぶ「御汲湯(献上湯)」が行われました。
1662年には病弱だった四代将軍家綱にも運ばれ、御汲湯が本格的にスタート。
八代将軍徳川吉宗の時代には1726年(享保11年)から1734年まで、9年間続けて行われたそうです。
運んだ湯樽の数はなんと3643個。
この江戸時代式「温泉宅配」は、いかにして行われたか?
100度近い大湯の源泉を、木の香立つ檜の桶に汲み入れ、人足が樽を担いで、江戸城までの28里(約110キロ)の道のりを昼夜兼行で走ったそうです。
湯の鮮度の証としてしっかり樽を封印し、道中一度も桶を地面に降ろすことは許されなかったといいます。
およそ14,15時間で到着し、吉宗は江戸にいながら適温で熱海の湯を堪能したと言われています。

時の将軍を代々魅了し続けた温泉。
その温泉を自宅で楽しもうという発想は江戸時代にはすでに始まっていたようです。
「温泉宅配」はまさに、大名気分で満喫できる娯楽、と言えるでしょう。
現代に生まれた私たちは、将軍でなくても、
将軍に献上されていたように貴重な「御汲湯」を満喫できるのです。
しくみはいたって簡単。
20リットルの宅配セット(5,940円、送料込み)、家庭用入浴器具「バスインバス」キット(9,800円)電動ポンプ(4,950円)
の3点があれば、自宅が温泉地に早変わり。手軽に温泉を楽しむことができます。
およそ400年前の徳川将軍の時代、人足たちが海を見ながら走ったであろう東海道の旅路に思いをはせながら、
家族以外は誰にも気兼ねせず、まさに大名気分で堪能する「温泉宅配」。
是非この機会に、お試しあれ。
■参考文献
松田法子、大場修「近世熱海の空間構造と温泉宿「湯戸」の様相」(2006)
松田忠徳「温泉はなぜ体にいいのか」(2016年)平凡社



浴槽いっぱいの250ℓのぽかぽか温泉をご指定の日時に専用電動アシスト台車でお届けいたします。ご自宅の浴槽を100%源泉でいっぱいに!至福の源泉100%独占タイムをお愉しみください。
温泉は、日光鬼怒川、那須からお選びいただけます。